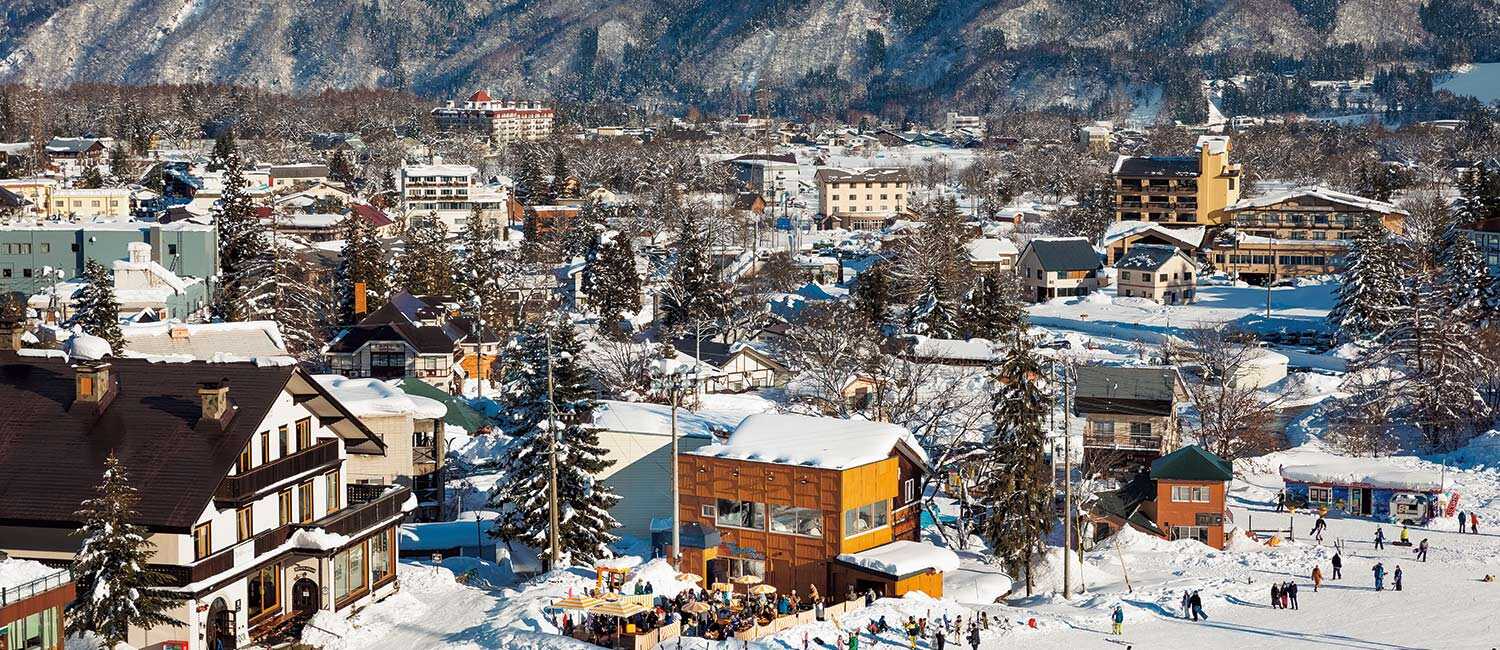〈マリーアイランガニー〉の“スリランカカレー”
マニアック系からイノベーティブまで、新しい才能が次々と現れ活況を見せる東京チャイニーズシーン。そのトップをひた走る〈ミモザ〉の南俊郎シェフがひそかに通う店は、意外にも スリランカカレーの店だった。決まってオーダーする一皿とは?
- SERIES:
- 注目シェフが教える感動の「名店メニュー」 vol.19

 ポークカレー(1300円)
ポークカレー(1300円)
塊でじっくり火を入れる豚肉は、ほろりと崩れる軟らかさで、ルウにも肉の旨みがたっぷりと染み出ている。茶色くなるまで炒めたタマネギのコクがリッチで、複雑かつ鮮烈なスパイスの香り、辛味がじわじわと効いてくる
〈ミモザ〉南 俊郎シェフ
 伝統を踏まえたクリエイティブな味
伝統を踏まえたクリエイティブな味4年半料理長を務めた〈シェフス〉で名店の評価をさらに上げ、2016年に現店を開業した南俊郎シェフ。上海料理の歴史、伝統を繋ぐ味に独自のクリエイションを織り交ぜた、華やかな料理で食通をトリコに。ニュウマン横浜〈ミズ カサブランカ〉など飲食店の監修も。
住所:東京都港区南青山3-10-40 フィオラ南青山ビル2F
営業時間:18:00~23:00 定休日:土曜・日曜 TEL:03-6804-6885
■南シェフ
カレーの先の美意識を味わいに
ガストロノミックなレストランからカジュアルグルメまで、好きな店の幅は広いが、外食する時間も機会も頻繁には取れないと話す南シェフ。となればリピートするのはさらに至難の業だが、ゲストの紹介で訪れたスリランカカレーの店〈マリーアイランガニー〉には、繰り返し通っているという。
「本当は教えたくないんですよ。通りすがりではちょっとわかりづらい立地ゆえか、いつお邪魔しても比較的静かで落ち着いて食事ができる。そのうえ、とても美味しいので。わざわざ行きたい店って、渋谷になかなかないですよね」
ビーフにチキン、牛挽き肉、鶏レバーと、全メニューを制覇し、一番好きになったのがポークカレーなのだとか。
「軟らかな豚肉はボリュームも十分で、とはいえガツン系とは違う、上品で優しい味。潔いほどシンプルな盛り付け、器選びから店の空間作りまで、すみずみに独特の美意識を感じます」
■志藤シェフ
義父の味を受け継ぎ手間をかけて
店のカレーの大きな特徴は「カラピンチャ(カレーリーフ)とランペ(パンダンリーフ)を両方使うこと」だと話す志藤シェフ。いずれも基本はスリランカ産のもの、加えて現地の職人がブレンドする香り高いミックススパイスも、重要な味の骨格になっている。
「店を開く前は、3年に2度はスリランカへ出向いて、スパイス作りの工程を見ていたのですが、刺激臭にまみれて行う大変な重労働。このスパイスあってこその店の味だと思っています」
炒めタマネギとトマトピュレ、肉、スパイス、ハーブを鍋に入れて、一緒に煮込んでいく調理法は、ホールスパイスを油で炒めて香りを移し、その油で具材を炒めるインドのカレー作りとは対照的。
「料理上手な義父が友人たちにふるまっていた家庭の味がベースで、本格スリランカ料理とはまた違う味ですが、カレーをきっかけにスリランカのことを知っていただけたら嬉しいですね」

Check1 スリランカの香辛料 上から時計回りに、ココナッツパウダー、粉状のミックススパイス、シナモンとクローブとカルダモン(すべてホール)。ホールスパイスは、噛んだときに弾ける香り、風味が鮮烈
上から時計回りに、ココナッツパウダー、粉状のミックススパイス、シナモンとクローブとカルダモン(すべてホール)。ホールスパイスは、噛んだときに弾ける香り、風味が鮮烈
Check2 長く炒めたタマネギ 油も塩も加えず、タマネギそのものの水分で火を通し、強火のままあえて焦がして、茶色いルウを作る。1回の仕込み量は約20個で、タマネギのルウ作りだけで2時間半以上かかる
油も塩も加えず、タマネギそのものの水分で火を通し、強火のままあえて焦がして、茶色いルウを作る。1回の仕込み量は約20個で、タマネギのルウ作りだけで2時間半以上かかる

マリーアイランガニー[MarieIranganee]
渋谷の雑居ビルの5階にある、知る人ぞ知るスリランカカレーの店。妻がスリランカ人と日本人のハーフという志藤幸光シェフ、義父がかつて東中野で営んでいたスリランカ家庭料理の店で修業し、2014年に店を開いた。その義父の伝手で仕入れるスリランカ産のスパイスやハーブと、2時間以上かけて炒めるタマネギが味のベースに。若き日はミュージシャンだったという志藤シェフ。BGMは'60 ~'70年代のロック、至るところに希少なポスターやアーティストグッズがちりばめられた店内には、男の秘密基地感が漂う。 バーだった店舗を改装
バーだった店舗を改装  しょう油が隠し味のスペアリブ1000円
しょう油が隠し味のスペアリブ1000円 ボブ・ディラン監修のウイスキー“ヘブンス ドア”も揃う。1杯3000円~
ボブ・ディラン監修のウイスキー“ヘブンス ドア”も揃う。1杯3000円~ 尊敬するディランのTシャツにハンチングで、厨房に立つ志藤シェフ
尊敬するディランのTシャツにハンチングで、厨房に立つ志藤シェフ

●マリーアイランガニー
住所:東京都渋谷区宇田川町34-6 M&Iビル5F
営業時間:11:30~14:30(L.O)、18:00~21:00(L.O)
定休日:月曜
TEL:03-6455-3216
雑誌『Safari』10月号 P168掲載
“名店メニュー”の記事をもっと読みたい人はコチラ!
photo : Jiro Otani text : Kei Sasaki