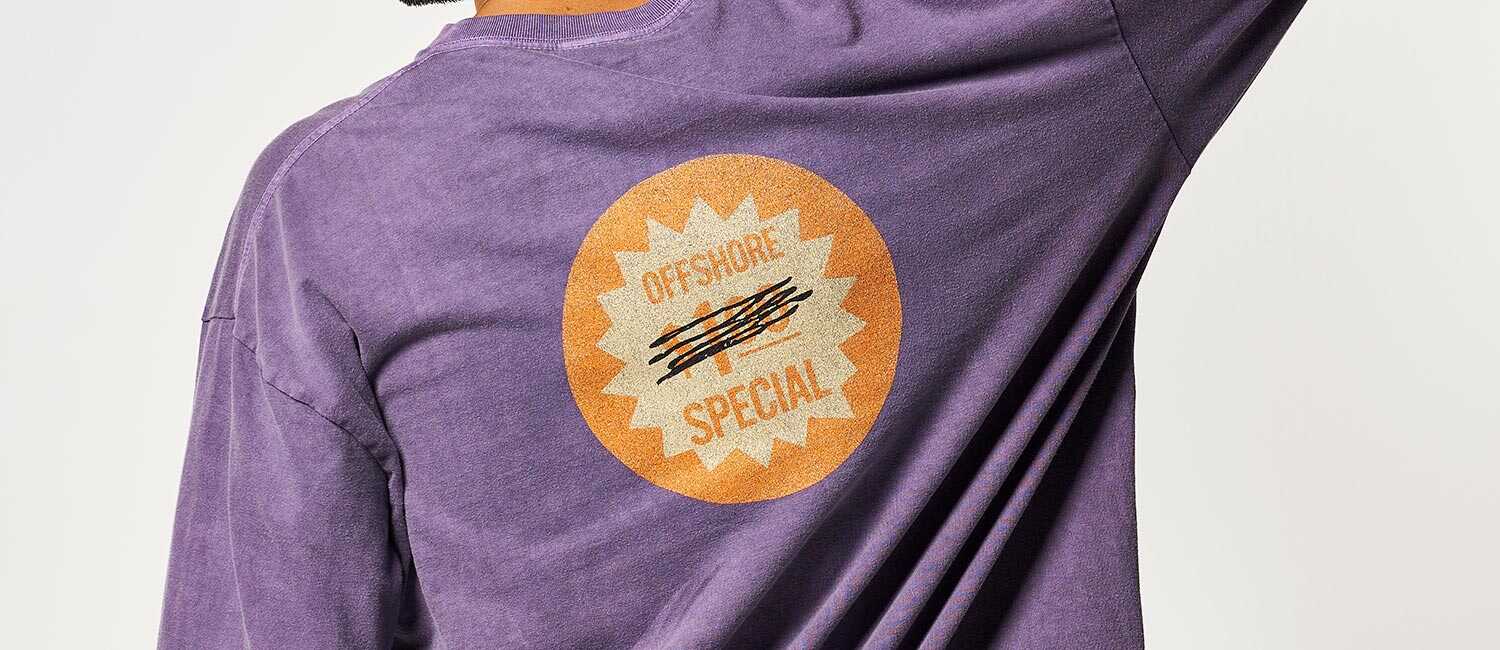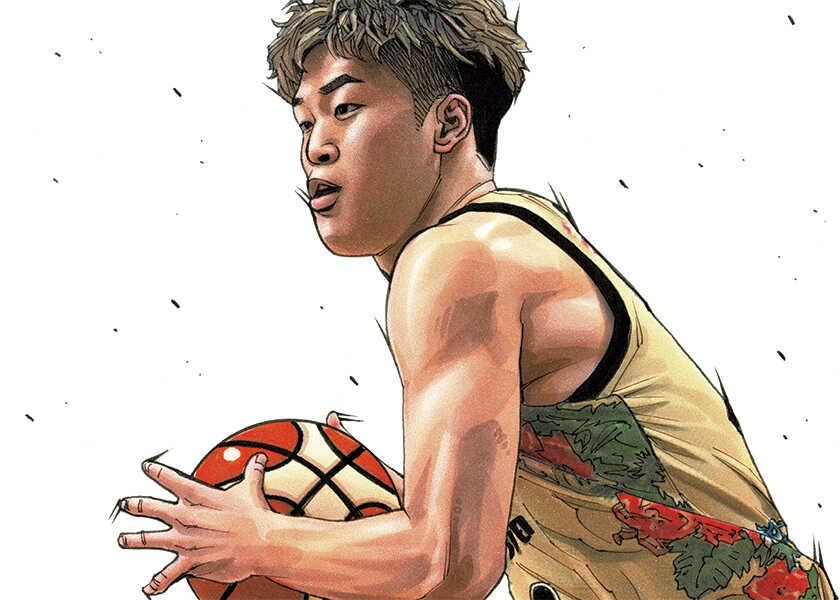映画『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の原作、『花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』(早川書房刊、文庫本のタイトルは『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン オセージ族連続怪死事件とFBIの誕生』)は、ジャーナリストのデイヴィッド・グランが100年前のオクラホマ州で起きたネイティブ・アメリカンの連続殺人事件を、10年以上を費やして調べ上げた執念のルポルタージュだ。
本書はいくつかの要素で構成されている。ネイティブ・アメリカンのオーセージ族居留地で次々と起きた殺人事件や怪死事件。発足したばかりの捜査局(FBIの前身)から派遣されたトム・ホワイト捜査官による捜査と裁判の顛末。事件の背景にあるネイティブ・アメリカンが辿った苦難の歴史。そして著者であるデイヴィッド・グランが100年前の事件を掘り下げることで明かされた、さらなる陰謀の存在……。
スコセッシ監督が、長大な原作本をオーセージ族の女性モリーとその夫アーネストを軸にして脚色したことはすでに述べた。原作ではトム・ホワイト捜査官の生い立ちや事件後の経歴、そして彼が所属したFBIが事件に及ぼした功罪についても多くのページを割いているが、映画『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ではホワイトの出番は最小限に留められているし、早々に事件解決をアピールしたかったFBIが、アーネストの叔父ウィリアム・ヘイルを有罪にする以上の全貌解明を望まなかった事情も描かれていはいない。

しかし注意深く映画を観てみると、スコセッシがどれだけ丹念に、原作本が迫っていたオーセージ族の苦難の歴史や、権力者の横暴について触れていたのかがわかる。その例をいくつか紹介しておきたい。
まず映画の冒頭ではオーセージ族の儀式が描かれる。そこでは儀式用のパイプを埋葬し、先祖に対してオーセージ族の伝統が失われ、白人文化に侵食されていくことを嘆いている。実際、劇中ではリリー・グラッドストーンが演じたモリー・カイル(結婚後の姓はバークハート)は100%オーセージ族の血を引いているが、7歳だった1894年に強制的にカトリック系の寄宿学校に入れられている。家族や部族から引き離されて、キリスト教の価値観に基づいた英語教育を受けさせられたのだ。
当時のアメリカ政府のネイティブ・アメリカンへの施策は、彼らの土地を奪い、荒れた土地の居留地に押し込めるか、もしくは絶滅させることだった。代々暮らしたテリトリーを追われた彼らは狩りや戦士の風俗を禁じられ、白人文明に同化し、土着して農耕民になることを強いられた。オーセージ族が例外的に裕福になれたのは、居留地になる土地を事前に自分たちで購入し、偶然にも地下に豊富な石油資源が眠っていたおかげだった。しかし彼らの石油の受益権を狙う輩たちのせいで膨大な数の同胞が殺されたのだから、幸運だったと言い切るのは難しい。

冒頭のシーンでは、儀式を外から覗いている少女と少年の姿が映される。2人はモリーと、後に成長してウィリアム・ヘイルの友人となり、射殺死体で発見されることになるヘンリー・ローンだろう。劇中でも少しだけ触れられているが、モリーとヘンリーは部族の掟によって10代半ばで夫婦になった。あくまでも慣習上の婚姻で法的なものではなく、成長した2人は別の相手と結婚しているのだが、一瞬だけ映るまだあどけない2人はオーセージ族を襲う嵐の強烈さをまだ知らずにいるのである。
その冒頭と対称を為し、また映画全体を挟み込んでいるのが、スコセッシらしい俯瞰で撮影されている同心円状のダンスだ。これは毎年6月にオーセージ郡で開催されている『イン・ロン・スカ』というお祭りで、廃れていく伝統を継承し、共同体の結束を強める役割を果たしているのだという。
スコセッシは映画の最初にオーセージ族の伝統が失われる前兆を描き、“恐怖時代”と呼ばれた最悪の時期を描き、そしていまも自分たちのアイデンティティを失うまいと抗い続ける彼らの底力で映画を結んでいる。つまり、映画の本筋はアーネストとモリーの夫婦の間の裏切りの物語であり、叔父ウィリアム・ヘイルを画策した陰謀劇なのだが、映画全体を俯瞰してみれば、もっと壮大なスパンでオーセージ族の苦難とサバイバルを描いているのである。(PART4に続く)
※本記事は4部構成になっております。

画像提供 Apple / 映像提供 Apple