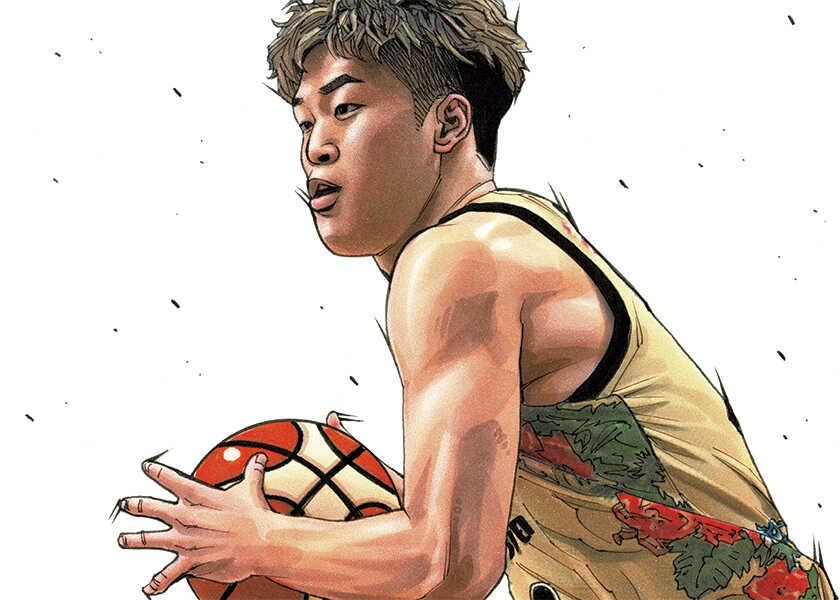2023年の最新作『オッペンハイマー』(全米公開は7月21日)が盛大に絶賛を集めているクリストファー・ノーラン監督(ただし原子爆弾の開発者を描くという題材が懸念され、いまだ日本公開の目処は立っていない)。彼自身が敬愛するスタンリー・キューブリックの後継とも言われるほどの完璧主義者で、コロナ禍で皆が一気にストリーミングサービスに傾いたなか、ほぼ孤軍奮闘で(同志はトム・クルーズくらい!)劇場公開の大型映画にこだわり続ける現代の巨匠。
そんな1970年ロンドン生まれの彼がハリウッド&世界におけるトップエリートの座を揺るぎないものとした代表作が、2008年の『ダークナイト』だ。ご存じDCコミックの映画化企画で、“バットマン三部作”の真ん中に位置するもの。しかし第一作『バットマン ビギンズ』(2005年)と第三作『ダークナイト ライジング』(2012年)が、やたら地味だったり(前者)、お話が粗雑だったり(後者)したせいで、誰もがトリロジーであることを忘れたように、『ダークナイト』が単独で伝説の名作として屹立する結果となった。


『ダークナイト』が映画史に残したツメアトは当然深くて強烈なものだが、その跡形は主に3つある、と言えるかもしれない。
まずひとつめは、基本的に能天気ジャンルだったアメコミのスーパーヒーロー映画を、とびきりシリアス(社会派)に仕立てたこと。もちろんティム・バートン監督の『バットマン リターンズ』(1992年)という社会(リア充)から疎外された怪人たちの暗黒な内省を描く特殊な傑作も先行例としてあったが、『ダークナイト』は明確に9.11以降の“正義”の行方を問う構造を取っていた。
どういうことかと言うと、2001年9月11日、旅客機をハイジャックして米ニューヨークの世界貿易センタービルに突っ込んだイスラム過激派が、あくまで自分たちの“正義”を信じてテロを行ったように、もはや何が“正義”だかわかんない混迷の時代相が映画のストーリーに反映されているのである。本来“悪の化身”であるジョーカーは、ゴッサムシティで大暴れにして市民社会を大混乱に陥れるのだが、しかし“正義”を担うはずのバットマンに「俺はお前と同じだ」と告げる。善悪の概念に囚われず、徹底した自由意志で気まぐれに行動するジョーカーは、まるで無邪気な子供がゲームで遊んでいるようだ。そんななか、コインの表裏のように、悪と戦う好青年だった検事ハービー・デントが、凶悪な復讐心の権化であるトゥーフェイスへと裏返る。「それってあなたの感想ですよね?」という風に、あらゆる“正義”が相対化されてしまう。こうした多様の形や立場の“正義”を撹乱させるキープレイヤーの前に、バットマンはひたすら悩み続け、あっけらかんと破壊を繰り返す宿敵ジョーカーが主人公の座を実質的にジャックしたのであった。


確かに“ヒーロー映画”とは、何よりも時代の映し鏡であり、“正義”とは何か?を問う要素を持ったジャンルだと言える。その基準や所在が揺らぐとヒーローの存在意義そのものが危うくなるのだ。この現代的なリアルを社会時評のように示した『ダークナイト』が批評・興行ともに大成功したことで、影響と刺激を露骨に受けたのがDCのライバルであるマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)である。
『ダークナイト』とほぼ同時期に公開されたMCU第一作『アイアンマン』(2008年/監督:ジョン・ファヴロー)は、まさに従来的なヒーロー映画の延長にあるイケイケの能天気路線だった。『アベンジャーズ』(2012年/監督:ジョス・ウェドン)とかもかなりの明るいバカ路線だったが、しかしアントニー&ジョー・ルッソ兄弟が監督を務めた『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』(2014年)や『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016年)あたりから、MCUは人格が豹変したようにグッとシリアスで知的になる。


人種差別の抗議運動“ブラック・ライヴズ・マター”と連結する『ブラックパンサー』(2018年/監督:ライアン・クーグラー)、リベラル多元主義と排他的な全体主義の戦いを象徴させたルッソ兄弟の『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018年)や『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)へと続く流れは、ドナルド・トランプ政権時代の混沌を見据えながら併走する“政治映画”の顔をバリバリ強めていった。もちろんDCユニバースも基本的には同様で、あの格差や分断を抉る問題作にして傑作『ジョーカー』(2019年/監督:トッド・フィリップス)も、『ダークナイト』の成果なしには生まれ得なかったはずだ。(後編に続く)

●noteでも映画情報を配信しています。フォローよろしくお願いいたします!
https://note.com/safarionline
Photo by AFLO