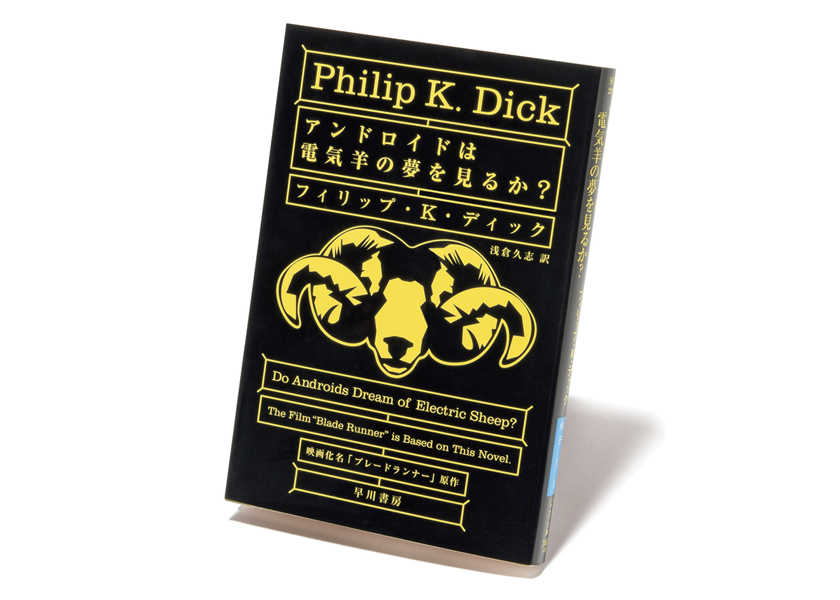『ホワイト・ジャズ』×ロサンゼルス
ジェイムズ・エルロイの暗黒のLA四部作の末尾を飾る『ホワイト・ジャズ』は、映画や興行で華やいでいた1950年代のLAのダークサイドを描いた徹頭徹尾ノワール作品だ。冲方丁や馳星周といった個性派作家に多大な影響を与えたエルロイ文体にどっぷり浸ると、転落と破滅のドライブ感、さらには当時のLAの腐臭が漂ってくる。
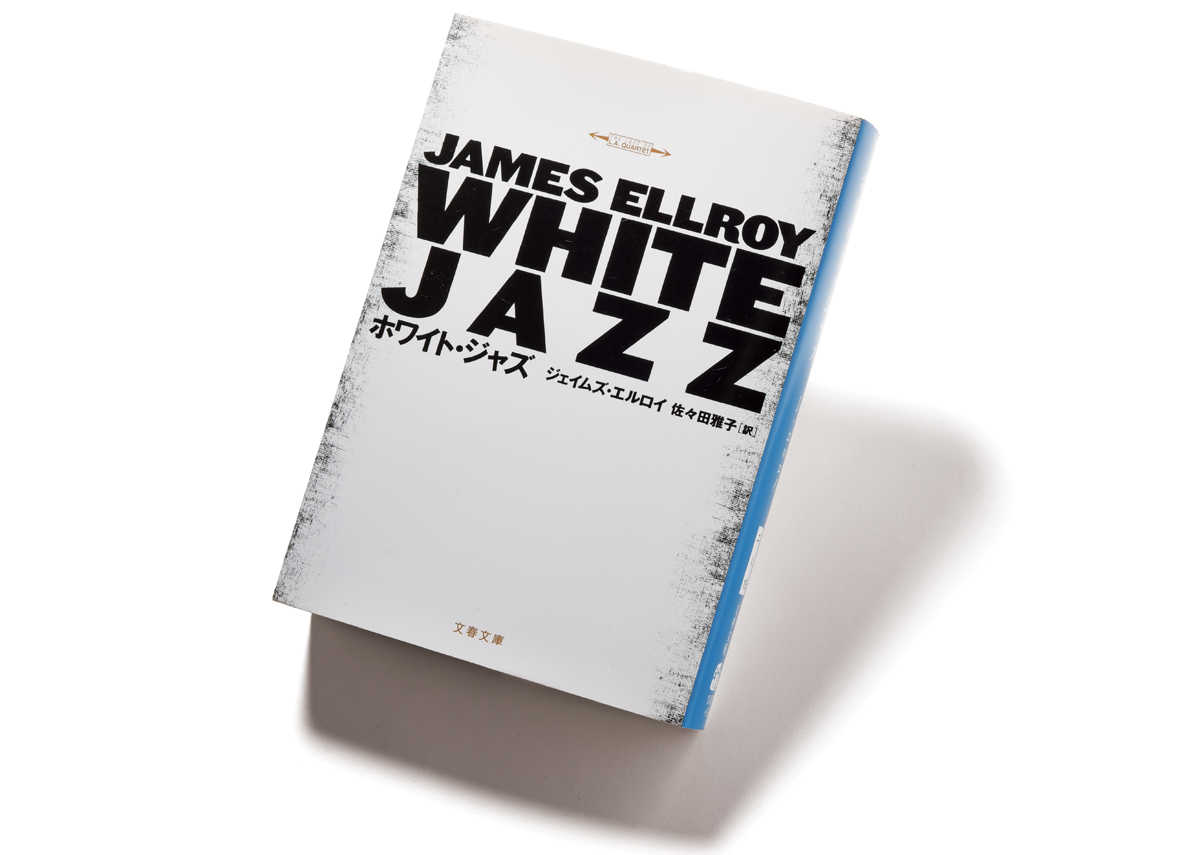
ブツ切りの単語の羅列がなんだか心地いい
著者ジェイムズ・エルロイの『ブラック・ダリア』『ビッグ・ノーウェア』『LAコンフィデンシャル』に続き、暗黒のLA四部作のフィナーレを飾るのが本書だが、これが特に大クセだ。まずは斬新な文体。「ユニヴァーシティ署。逮捕/手口――なし」「今=空気を吸う、ひと息苦しい――ジョニーが俺の譫妄状態を再生する」
といった具合の、電文調とも評される「エルロイ文体」が全編で貫かれる。/や=といった記号が乱れ飛び、Q数や改行は規則性を持たない。リズムを作っているのか壊しているのか判然としないが、ジャズとも呪文とも思える文字の羅列を読み進めていくうちに、名状しがたいスピード感を伴ってゆくのは鬼才エルロイの意図なのだろうか。
描写についても長ったらしい比喩などは作中では好まれない。接続詞が省かれ、小説などではタブーとされる体言止めの連続もいとわず、表現というより名詞や事実の連続だ。
しかしそれはなにより、ページを手繰る者の想像を促してゆく。断片を推理して繋ぎ合せていく作業が楽しい。まさに読書の本懐ここに極まり、といった感じなのだ。
ところで『ホワイト・ジャズ』の物語はLA市警の警部補デイヴィット・クラインの一人称で語られる。1950年代のロサンゼルスはギャングや麻薬の売人、八百長ボクサーに計算高い女優、止まない欲を抱いた富豪や政治家、覗き屋や情報屋が跋扈する暗黒社会だ。まさに「全員、悪人」。この世界では真実の優先順位は極めて低い。大切なのはなにより富と名声、そして命だ。
クラインももちろん、その1人、悪徳警官としてこのノワールを暗く激しく彩る。序盤から裏金をせびり、証人の元ボクサー、サンダーライン・ジョンソンを窓から放り出し、「ジョンソンは空を飛べると言い出しました」ととんでもない供述を口にする。
しかし、それこそが彼の転落のはじまりだった。上司からは咎められ疑われ嵌められ、マフィアからは狙われ追い詰められ殺されかける。窮状が続くクラインのハードボイルドな処世術は必見だ。
同時に恋人に「実行の人」と呼ばれる彼の冷静かつ大胆な思考と衝動、それが引き起こす静寂と喧騒が絶妙なコントラストで読者を覆う。いや、蝕んでいくと表現すべきか。
天使が住む街、ロサンゼルス。温暖な気候と陽光降り注ぐ理想郷とも言えるが、本作ではその光は「ぎらぎらとまぶしい」と忌まわしきものとして扱われる。
自然と都市が高次元でハイブリッドされた現在のLA。しかしほんの70年前は国家レベルの黒い歴史が色濃い、裏切りと腐敗にまみれた暗黒街でもあった。
さて、どちらのLAが本来の姿だろうか。あるいはその極端な二面性こそがこの街最大の魅力なのかも。
●『ホワイト・ジャズ』
ジェイムズ・エルロイ著 佐々田雅子訳 文春文庫 1170円
雑誌『Safari』2月号 P187掲載