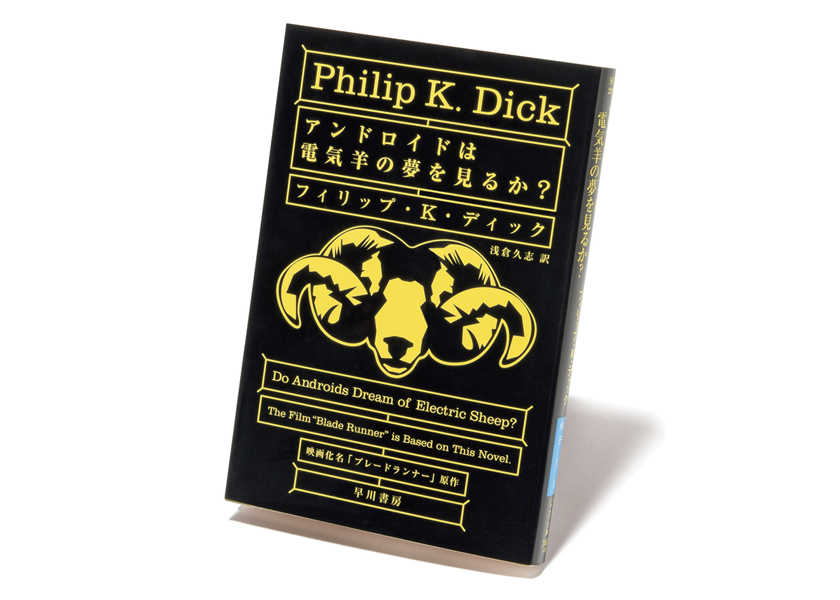『紙の民』×LA
2011年に発売された紙上で繰り広げられる戦争を描いた『紙の民』。この作品はメキシコ出身の作家、サルバドール・プラセンシアの意欲作として名高い1冊だ。縦横無尽に展開され、ときには黒塗りになった部分もある斬新な本文レイアウトは、読者への挑戦であり、文学の可能性を広げる試行でもある。無限に広がるトリッキーな物語。その中にこめられたメッセージを読み解いてみよう!?
- SERIES:
- AMERICAN BOOKS カリフォルニアを巡る物語
“土星と戦う”って一体なんのこと?
奇想天外なのに愛してしまう話題の1冊!
“ここまでもおかしくて悲しいメタフィクション”“オリジナルが強すぎて、物語に追いつけなかった”“この作品を理解できれば本読みとして次のステージが開ける”。メキシコ出身の鬼才、サルバドール・プラセンシアのデビュー作である本作はプロアマ問わず、様々な議論を巻き起こし、書評家たちを悩ませ続けた。そしてそれはいまだ決着していない。あるいは決着しないことがこの作品の最大の魅力なのかもしれない。
国境を越えてメキシコから“サンタフェ・トレイルの終点”である西海岸カリフォルニア・エルモンテにやってきた父娘。彼らをはじめ、登場人物たちは上空から監視する“土星”に宣戦布告し、紙の民として抵抗をはじめる。その土星こそが作者のプラセンシアなのだが、登場人物に“土星は俺たちをクライマックスに持っていって、そのあと結末に持っていきたいわけだ”と言わせてしまう作品など、なかなかお目にかかれないだろう。
実際、米文学研究家の柴田元幸は帯で“訳すには種々の困難が伴うこの小説”と大々的に嘆いたように、噛み合わないストーリー、形を変えて決して定まらないレイアウト、黒で塗りつぶされた部分の挿入など、あまりに実験的でエキセントリック。本による表現の幅を広げたともいえる意欲的で希有な作品である。
自ら火傷を負い夜尿症を強引に治したフェデリコ、架空のレスラーとされるサヤマサトル、蜜蜂の針の中毒になってしまう女や盗人の教会など。ちりばめられた登場人物や舞台装置はそれぞれ、SF短編を描くことが可能なように秀逸なネタの連続で、罠と伏線の役割も果たしている。訳者あとがきで文学青年であったプラセンシアがガルシア=マルケスの『百年の孤独』を繰り返し読んでいたことに触れているが、着地点の難しいストーリーの連続はなるほど、それも納得だ。
また、その突飛なアイデアの陰に隠れがちだが、誰もが抱いている悲しみや痛みからの脱却=自由や自己を得るという意味ではアメリカ文学の核心を突いている。さらにドラッグや人身売買など、北中米にはびこる社会問題をも風刺する示唆にも富んでいる。同時に新鮮なライムの香り、性行為の臨場感などの描写は巧みで、あらゆる角度から読み手の共感と好奇心を刺激し続ける。そして、ある種の混沌の中だからこそ「愛に一売女あり」「ハグとキスの畑だね」「きみの匂いがしなくて寂しいよ」といった愛や性に対する文言が浮き上がるのである。そのすべては美しい名文「悲しみに続編は存在しないのである」に導かれてゆく。
アメリカの文芸誌が選んだ“世界で最も独創的な作家50人”に村上春樹らと選ばれた作者のプラセンシア。彼が描くマジック・リアリズムは不朽だ。個人的には聖書、漢詩名作選などと同じく、無人島に携え繰り返ししがんで深く味わう本として有用なのではないかと思うが、アナタの書評はいかがだろうか?
●『紙の民』
サルバドール・プラセンシア 著 藤井 光 訳
白水社 3700円
雑誌『Safari』6月号 P279掲載