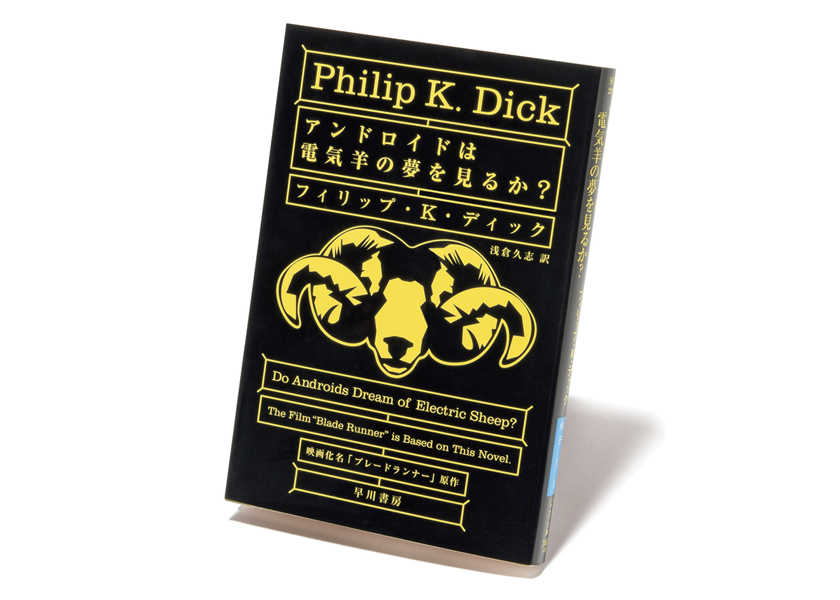【Vol.33】『パルプ』×LA
暇さえあれば、いや、暇がなくても、バーと競馬場に入り浸り、ろくに仕事もしない私立探偵のニック。彼のもとに死んだはずの作家を捜索する依頼が届く。それを皮切りに、奇妙な事件に次々と巻きこまれていく。死に神や浮気妻、宇宙人などが入り乱れ、物語は佳境へと向かう。LAを代表する作家ブコウ…
- SERIES:
- AMERICAN BOOKS カリフォルニアを巡る物語
暇さえあれば、いや、暇がなくても、バーと競馬場に入り浸り、ろくに仕事もしない私立探偵のニック。彼のもとに死んだはずの作家を捜索する依頼が届く。それを皮切りに、奇妙な事件に次々と巻きこまれていく。死に神や浮気妻、宇宙人などが入り乱れ、物語は佳境へと向かう。LAを代表する作家ブコウスキー最後の長編小説。過去の作品を思わせる記載やキャラも登場。オールドファンは思わずほくそ笑んでしまうはず!
LAはフィリップ・マーロウものをはじめ、数々のハードボイルド探偵小説を生み出してきた。夢を求めてLAに来た雑多な人々が起こす、あるいは巻きこまれる犯罪を、タフな探偵たちがカラダを張って解決する。彼らが女や酒にちょっとだらしないのも、欲望の町LAに似合っていて、そこがまた魅力である。
それにしても……、酔いどれ詩人として名高いチャールズ・ブコウスキーがハードボイルド探偵小説を書くと、ここまでだらしない探偵が出来上がるのか! なにしろ主人公のニック・ビレーンは、「俺はLAとハリウッド両方で一番の私立探偵」とうそぶきながら、酔っ払ってばかり。ろくに仕事がないのでオフィスの賃貸料が払えず、家主から追い立てを食らっている。冒頭、セクシーな声の女性から電話があるが、二、三言交わしたところで、「ジッパーを閉めなさい」と叱られる始末。実のところ、自ら認めるように「何ひとつ解決できない探偵」なのだ。
電話の女は死レ イディ・デスの貴婦人と名乗り、セリーヌを探してくれと言う。セリーヌとは30年以上前に死んだフランスの作家のこと。わけのわからない依頼だが、物語はこんな調子で、かなり行き当たりばったりに進む。といっても、“ハードボイルドのパロディを書こう”といった意気ごみはブコウスキーにはない。自画像的なキャラクターを使い、とんでもなく猥褻な言葉を口にさせて、思いつくままに書いている感じなのだ。ニックが次に受ける依頼は“赤レッド・スパローい雀”を探してくれというもの。手がかりもなく、ただ「どこかにいることは間違いない」というだけだ。さらに次の依頼は、宇宙人につきまとわれているからなんとかしてくれ、というもの。ハチャメチャぶりが半端ない。
ニックはこうした事件を解決しようと勇んで町に出る。「典型的なロサンゼルスの昼――スモッグ、半分出た太陽、もう何か月も雨はなし」(P94)。しかし、結局酒場で飲んだくれたり、ハリウッド・パークの競馬場に行ってしまう(作者同様、ニックは異常な競馬好きで、金をスッてばかりいる)。人妻のクルマを追っているときは、警官にクルマをとめられ、運転免許更新の筆記試験に落ちたことがばれ、思い切り笑われる。計画性のなさから危ない目にあうことも多く、そういうときは暴力行為で切り抜ける。失敗すると落ちこみ、自殺を考えたりもするが、やっぱり飲んだくれる。それでいて、なんとなく事件が解決していくいい加減さ。最後まで行き当たりばったりなのだ。
これはブコウスキーの長編としては最後のもの。病気で中断しながら書き上げ、死の直前に出版された。となると、ニックがたびたび人生を振り返り、「ここで俺が死んでも、世界じゅう誰ひとり、一滴の涙も流さないだろう」(P252)なんて感慨にふけるのも、けっこう本音の吐露ではないかと思えてくる。それでいて、最後まで自堕落ぶりを通すところがブコウスキー。これこそ彼の生き様だ。
●『パルプ』
チャールズ・ブコウスキー 著 柴田元幸 訳 筑摩書房 840円
雑誌『Safari』10月号 P223掲載