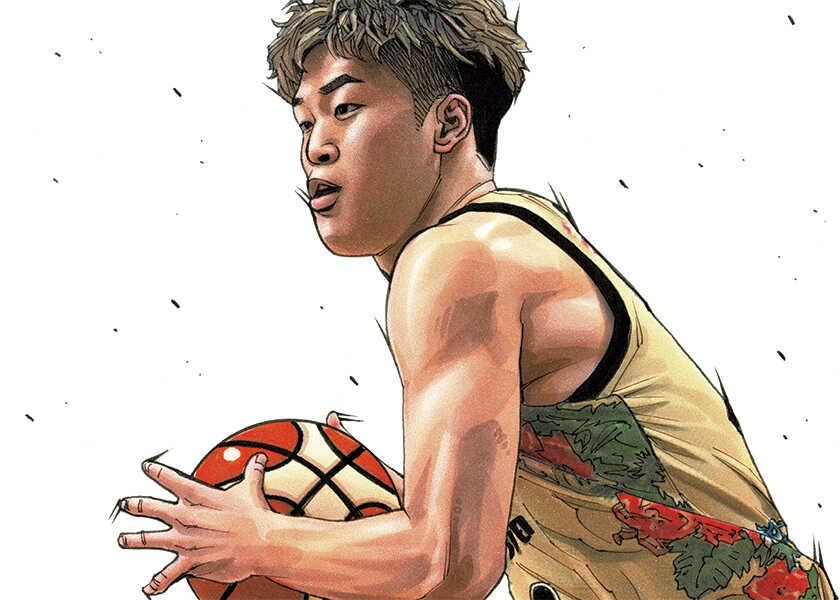2022.08.30
『トップガン マーヴェリック』が映画史に刻んだもの。そして、トム・クルーズが時代を超えて愛され続ける理由(後)


“父の不在”で読み解くトム・クルーズ映画の魅力
最後に、トム・クルーズのキャリアを通じて見えてくるものにも一言触れておきたい。
もともと、持ち前の美形とブレのない存在感を前面に押し出した『卒業白書』(1983年)や『栄光の彼方に』(1983年)で人気を博しつつ、『トップガン』(1986年)の頃にはすでに俳優としての域を超え、物怖じせず脚本や企画にバンバンと口を出す人間として知られていたトム。
彼は若き日に「最初からヒットを見越して作られた映画なんて、ありえないんだ。(中略)ただ最善を尽くし、信じた方向を目指すだけだ。そうすれば、たとえ興行的に成功しなくても、何らかの収穫が得られるわけだからね」*と語っているが、『ミッション:インポッシブル』(1996年)でプロデューサー業に乗り出してからは、さらに輪をかけるように自分の心とカラダを”最善”の状態へ追い込みながら、率先してエンタテインメントの局地を目指すようになった。
そんな彼のフィルモグラフィを紐解く上で欠かせないのが“父の不在”というテーマだろう。『トップガン』をはじめ、初期の主演作にはこれが色濃く登場するが、そこには家族から離別した末に亡くなったトムの実父に関する記憶が投影されていると言っていい。彼は80年代の初め、余命わずかとなった父と再会している。こういった実人生における忘れ難い経験が彼の映画づくりや役作りに及ぼしている部分は大きいのだ。
やがてトムが中年期に差し掛かると“不在”の色合いは一旦は弱まる。しかし歴史や人生は巡りめぐるもの。いつしか彼自身が父の齢に達すると、“不在”は再び、これまでとは全く別の形となって作品に現れるようになった。『トップガン』シリーズを例にとるなら、かつて父を亡くした主人公は、同じく父を亡くした青年のよき親代わりでありたいと懸命にもがき続ける。そこには親の立場と子の立場の深い呼応がある。どちらも身に覚えのあるトムだからこそ体現できた境地なのだ。
たとえ映画というものが壮大なフィクションの産物であったとしても、完璧主義者のトムは常に自らの心とカラダを駆使することでリアリティを最大限つかみ取って自分の血肉にしようとする。こうやって観客に対しどこまでも誠実かつ正直であろうとする姿勢こそ、トム・クルーズと彼の作り出す映画の最大の魅力であることを我々は忘れてはならない。
50歳で亡くなった実父の人生を超えて、今では人として、俳優として“未踏の領域”を飛び続ける彼。『トップガン マーヴェリック』は間違いなく、現時点における集大成的作品となった。だがこれも決して最終地点ではない。
これから目指すその先に、一体どんな景色が広がっているのか。年齢に応じて味わいを増していくトムの新作をこれからも楽しみに待ち続けたいものだ。(前編、中編はこちら)
*『誰も書かなかったトム・クルーズ』(集英社、1996年)ウェンズリー・クラークソン著、矢崎由紀子訳
文=牛津厚信 text:Atsunobu Ushizu
photo by AFLO
photo by AFLO