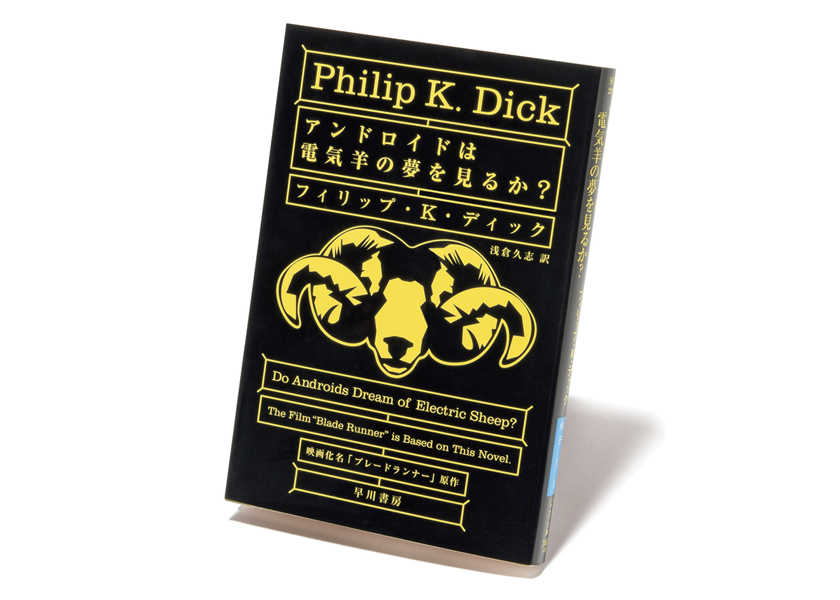『地下街の人びと』 × SF
地下室や暗いアパートが根城であるところから、“地下の人びと”といわれる人間たち。本作は、そんな彼らを主人公に、1950年代のサンフランシスコを舞台にしたある恋の物語。
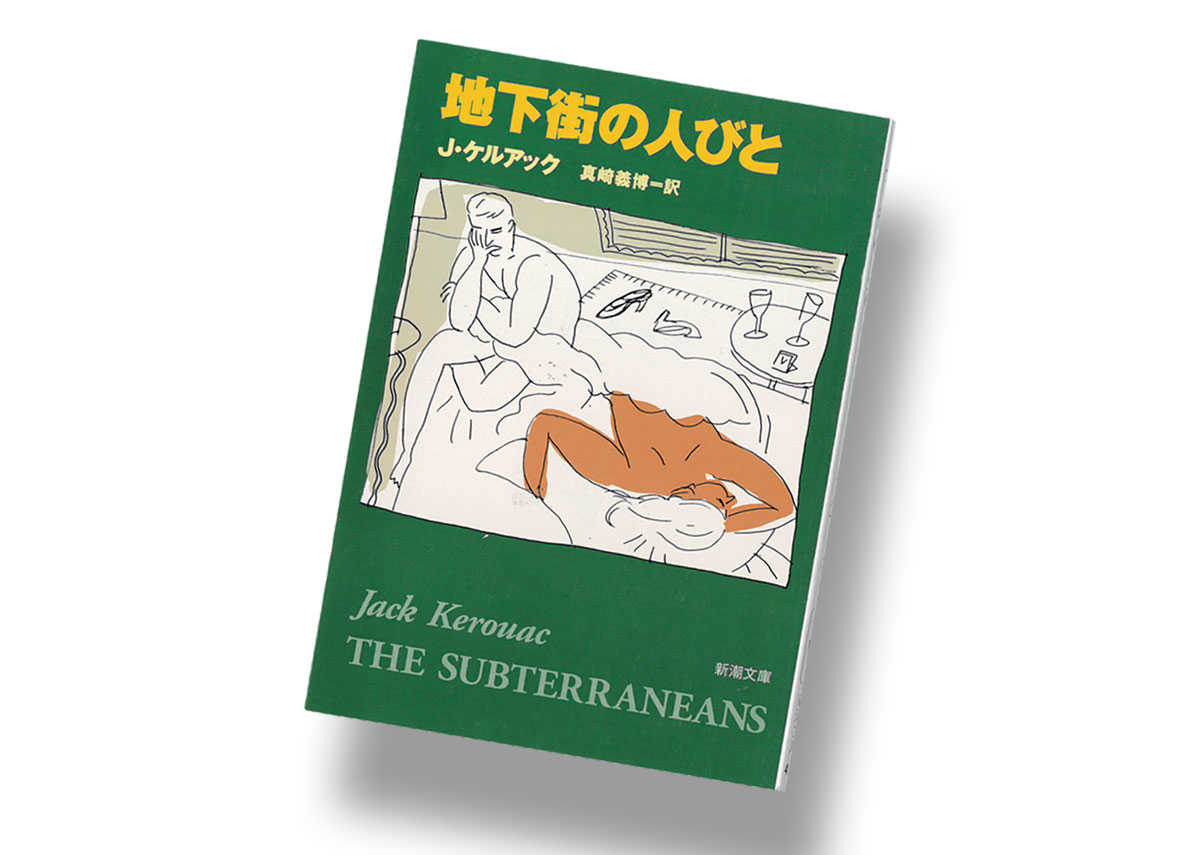
男女の刹那的な愛を描くビート小説!
刹那的だけど、情熱的だった恋の炎が消えたときビートジェネレーションの旗手、ジャック・ケルアックの胸に去来した感情とは一体なんだったのだろうか? 躍動する主人公たちの動きに、言葉にそして思考に、当時のSFの街の雰囲気も十分に感じられる作品だ!
自らの放浪紀行でもあり私小説的な側面を持つ『路上』で知られるビートの寵児、ジャック・ケルアック。
よく耳にするワードだが、そもそも“ビート”とはどんな概念なのだろうか?諸説、あるいは解釈の違いこそあるが、1950年代の半ばから既成の社会から酒やドラッグ、音楽の力を借りて解脱するボヘミアン的な生き方、およびその思想とするのが一般的だ。そして、“ビート”の語源は“BEATIFIC”(至福を与える)や、ジャズで用いられる“BEAT”(拍子)と考えられている。 今月紹介する『地下街の人びと』ではまさに、モダンジャズの原型であるビバップスタイルの創世者の1人、チャーリー・パーカーの存在がある。物語の舞台はサンフランシスコ、ノース・ビーチ地区。パーカーのヒップな演奏を聞いた夜に、主人公で作家のレオと黒人女性マードゥの恋が走り出す。「男ってクレイジーね。みんなエッセンスを欲しがるわ。女がそのエッセンスなの」という彼女の言葉とともに。
ただ、その恋路は複雑というよりも整合性がなく、文章的な区切りや物語の起承転結に欠けると切り捨てる評者も存在する。確かに極めて乱暴にいってしまえば、女にフラれる男、というだけの物語で、それをケルアックはよくいえば丁寧に、悪くいえば鈍行で綴っている。
しかし、誤解を恐れずにいえば、恋愛など所詮そんなものではないだろうか?
花束や指輪が登場するトレンディドラマが正しいのか? 恋愛には細密的なリアリティがあり常に文学的なのだろうか?
そう考えると、恋愛の本質は、きれいごとだけでは成立しない、嫉妬や不安や裏切りにまみれたドス黒い奔流である事実を突きつけられることになる。
それよりもこの作品で読み解くべき、堪能したい点は、どこまでも散文的で紡がれる言葉の数々、ラップの源流であるポエトリーリーディングだろう。「偉大な散文は詩だし、偉大な韻文は詩なんだ」
ドラッグでハイになっているのか、それとも正常なのか、読み手の判断は難しいが、それこそが多くのものをミクスチャーしたあの時代の特徴だろう。そして、狂っているといえば誰にも否定はできないが、その一方で、ビバップでヒップな『地下街の人びと』がクールだとされていた当時のサンフランシスコで、狂っていない人間など果たしていたのだろうか? そんな思考こそ、読者にとって最大の収穫のひとつなのかもしれない。
時代は異なるが、似たムーブメントはあらゆるところに存在する。作中を通した独特の倦怠感も共通だ。読みにくいと敬遠する人のために、英国でいうなら映画『トレインスポッティング』、ドラッグこそ登場しないが日本文学でいえば『苦役列車』などが似たような香りを感じる作品。そうたとえれば、これから読み進める一助になるだろうか?
●『地下街の人びと』
ジャック・ケルアック 著 真崎義博 訳 新潮社 490円
雑誌『Safari』7月号 P199掲載