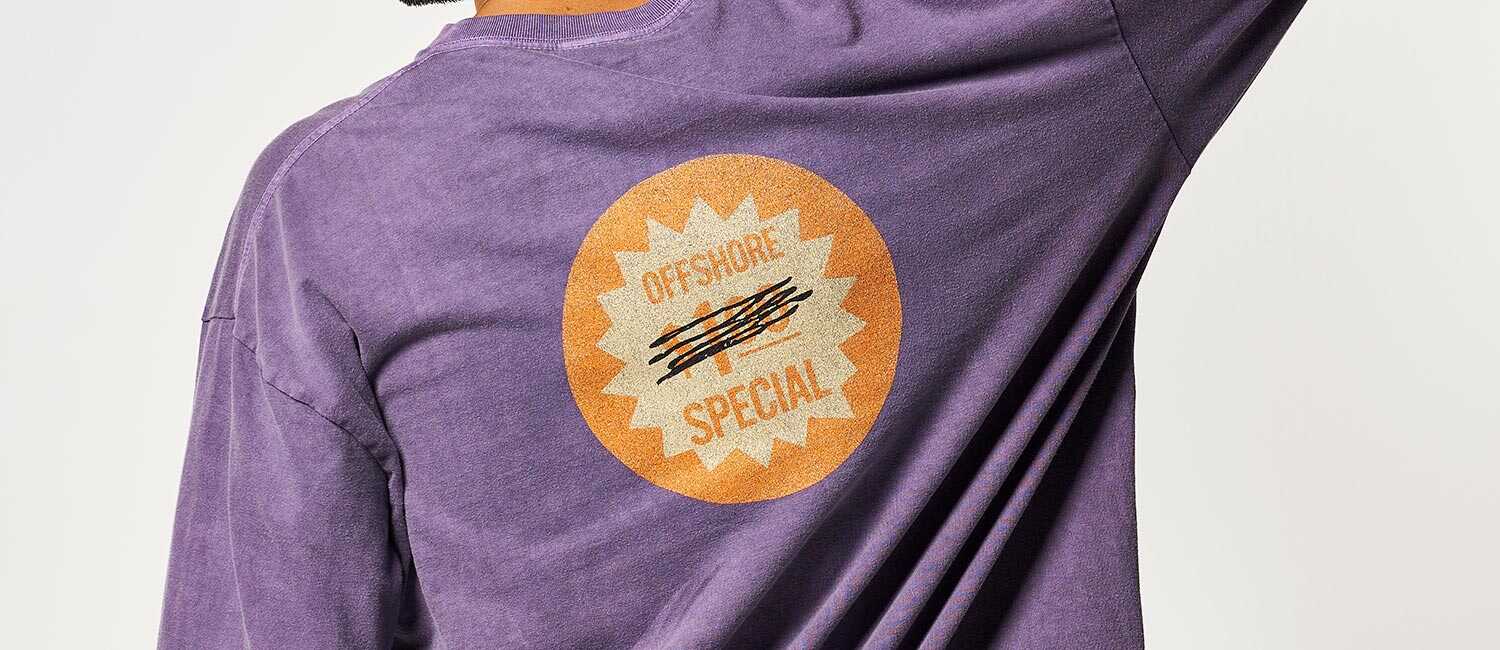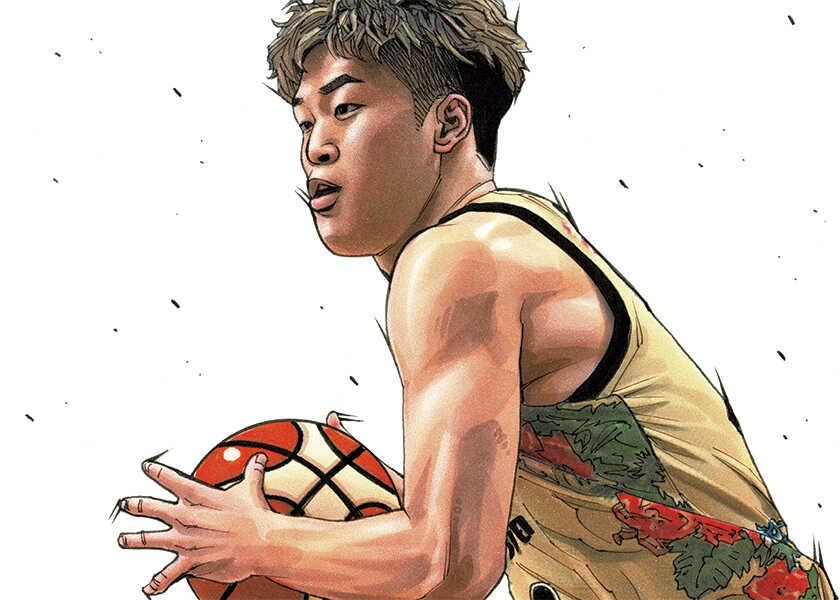だから、監督の“らしさ”を味わうのも映画鑑賞の醍醐味だ。で、今回は、監督の強い個性がビンビン伝わってくる映画をセレクト。さらに、気に入った監督に出会えたら、同じ監督作品を追って観ていくのも面白い。最近では、ヒット作の盗作疑惑が話題になっていたりするけど、もっと“監督らしさ”があれば騒動にはならなかったかも!?


デヴィッド・フィンチャー監督/『ゲーム』
製作年/1997年 出演/マイケル・ダグラス、ショーン・ペン、デボラ・カーラ・アンガー
観客を操る達人のテクニックが際立つ1本
ハリウッドきっての鬼才監督であるデヴィッド・フィンチャー。その作風は『セブン』に象徴されるように、ダークで冷徹。人間の暗部に光を当て、やたらと後味が悪くて、個人的にお近づきになるのはなんだかコワい……。そんなイメージをお持ちではないだろうか?
しかし、ある日突然妻が失踪してしまう『ゴーン・ガール』は大局的に見えればブラックコメディだし、『ソーシャル・ネットワーク』は青春ドラマ。さらに、『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』がファンタジーだし、『パニック・ルーム』はシンプルなスリラーだった。どれも映像的な工夫が凝らされていることや、有無を言わさぬ力強い演出技が冴えわたってはいることは共通していても、ジャンルは全く違っている。実はかなりバラエティ豊かなフィルモグラフィなのである。
そこでフィンチャーの凄みが詰まった快作としておすすめしたいのが1995年に公開された『ゲーム』だ。ネタバレが非常に懸念される内容なので紹介するのが難しいのだが、物語の発端は1枚の招待状。マイケル・ダグラス扮する主人公が、疎遠だった弟から「人生が一変する素晴らしい体験ができる」という“ゲーム”の参加権を贈られる。半信半疑のまま“ゲーム”に登録すると、周囲で次々と怪事件が起きるようになり、いつしか主人公本人が命の危険を感じるようになっていく……。
実はこの映画、フィンチャーが『セブン』で染みついた“怖い映画を撮る監督”というセルフイメージを思いっきり逆手に取っているのだ。『セブン』の監督なんだから、この先にはあんな展開、こんな展開が待ち受けているのでは?という観客の予想を利用して、思いがけないところまで連れて行ってくれる。そう、フィンチャーは、観る側の先入観すら織りこみ済みで、われわれ観客を操ってみせる達人なのだ。そして達人の手のひらでコロコロと転がされるのは、やたらと気持ちがいいものなのである。


クリストファー・ノーラン監督/『ダークナイト』
製作年/2008年 出演/クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー、マギー・ギレンホール
理論派にしか生み出せない傑作
クリストファー・ノーラン監督の作家性を表す言葉として“理論派”であることが挙げられる。物語のエモーショナルな要素も理論で解析するような作風は、ときに“理屈っぽい”と感じさせることもある。でも、“理論派”でしか撮れない傑作を1本挙げるなら、『ダークナイト』を置いてほかにない。
『ダークナイト』はノーランが監督したバットマン映画の2作めで、原作コミックにおけるバットマン最大の宿敵ジョーカーを登場させている。かつてはジャック・ニコルソンも演じたジョーカー役を、ヒース・レジャーがまったく新しいアプローチで怪演し、アカデミー助演男優賞に輝いた。
ノーランとレジャーが生み出したジョーカー像とは、カネや権力が目的ではなく、ただただ世の中をひっかきまわし、人間から醜い本質を引き出したいという超迷惑な“究極の愉快犯”。しかし犯罪が憎いという一心で、たった1人で悪党をボコって回るバットマンも、悪意と善意の違いだけで、やはり“愉快犯”とはいえないのか?
ジョーカーは、バットマンという存在が本質的に持っている矛盾をつまびらかにするカードの裏面である――という明確なコンセプトが『ダークナイト』の物語を哲学的かつ刺激的なものにしている。まさに“理論派”にしか構築できないノーラン節の真骨頂がこの映画には宿っているのだ。


ギレルモ・デル・トロ 監督/『シェイプ・オブ・ウォーター』
製作年/2017年 出演/サリー・ホーキンス、ダグ・ジョーンズ、マイケル・シャノン
幅広い引き出しを見せつけた恐るべき作家性
メキシコが生んだ奇才監督ギレルモ・デル・トロが、アカデミー作品賞、監督賞など4部門を勝ち取った本作。それまでは怪獣/ホラー/特撮オタクといわれてきたデル・トロが、B級路線では収まらない幅広い引き出しを持っていることを証明した作品だ。
聾唖のヒロインが、政府の研究所で拘束されている半魚人と恋に落ちるという物語自体は、いかにも従来のデル・トロらしい。実際デル・トロは幼い頃に観たB級ホラー『大アマゾンの半魚人』が着想の元になったことを認めている。ところが本作のテイストはB級どころか黄金時代のハリウッド映画のよう。得意とするダークファンタジーの要素はそのままに、多幸感あふれる煌びやかなミュージカルやラブロマンスへのリスペクトやオマージュにあふれている。
デル・トロ自信、筋金入りのオタクであることを認めている。サブカル以外の王道のアートにも同じように惹かれてきたと発言しているし、ハリウッド映画の教科書のような『素晴らしき哉、人生!』を獲った名匠フランク・キャプラの大ファンでもある。『シェイプ・オブ・ウォーター』はデル・トロという作家性の奥行きを感じさせる、文字どおりの集大成なのである。


アルフォンソ・キュアロン監督/『ゼロ・グラビティ』
製作年/2013年 出演/サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー
観客をエモーショナルにさせるテクが光る!
ギレルモ・デル・トロと並び、メキシコが生んだ天才監督として絶賛を浴びるアルフォンソ・キュアロン。そのフィルモグラフィは、刹那な青春を描いた『天国の口、終わりの楽園。』から近未来SFの『トゥモロー・ワールド』。果ては『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』まで広範なジャンルで彩られている。
また『トゥモロー・ワールド』で驚異の長回しワンカット(実際にはいくつかのショットが合成されている)を披露するなど、映像の魔術師としても知られている。そんなキュアロンは「一体どんな映画作家なのか?」という問いに答えてくれるのが、キュアロンがアカデミー監督賞に輝き、同時に技術賞各部門を総なめにした『ゼロ・グラビティ』だろう。
人工衛星の修理作業中だった女性宇宙飛行士ライアンが、大量の宇宙ゴミの飛来によって宇宙空間に投げ出される。酸素はわずかしかなく、救出も来ない状況下での、決死のサバイバルが描かれるのだが、キュアロンは本作をSFとして撮ってはいない。あくまでも“宇宙”は極限状態を描くための背景に過ぎず、フォーカスされるのは、一度は生きる希望を失った女性の魂のサバイバルなのだ。
本作においても、冒頭17分の長回しワンショット(これも合成の産物だ)など得意技を繰り出しているが、決して技術のひけらかしではない。宇宙にいるライアンの感覚を観客に共有してもらうための17分であり、技術もテクもすべてはエモーショナルなドラマに引きこむためのお膳立て。技巧派のようで“熱い”監督なのである。


ウェス・アンダーソン/『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』
製作年/2001年 出演/ジーン・ハックマン、ベン・スティラー、グウィネス・パルトロウ、ビル・マーレー
描かれる“人の繋がり“こそ真骨頂
最新作であるストップモーションアニメ『犬ヶ島』を例にとるまでもなく、いい意味で精緻な箱庭的世界を構築するのがウェス・アンダーソン監督のスタイル。シンメトリーを多用する構図、表情豊かとはいえないキャラクターたちが醸し出すユーモア、おとぎ話のような浮世離れしたムードなど、実写作品、アニメ作品を問わず、これほど作風が一貫している映画作家も珍しい。
そのウェス・アンダーソン的世界観が完成されたのが長編第三作めの『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』だ。舞台はニューヨーク。登場するにはひと癖もふた癖もあるテネンバウム一家の面々で、特に3人の兄、妹、弟は、子供の頃は天才ともてはやされ、今ではそれぞれに問題を抱えた中年になっている。
この問題だらけの顔ぶれが、大きく成長することなく、そしてベタベタと仲良くするわけでもなく、でも“家族である”というゆるい絆にたどり着く。そんなそこはかとない優しさにこそ、アンダーソン的世界の魅力の神髄がある。
これは血の通った家族だけに適用されるわけではない。『ライフ・アクアティック』の同じ船に乗った仲間たち、『ムーンライズ・キングダム』の同じ島に暮らす住人たちもまた、同じように“疑似家族”としてゆるい絆を深めていく。価値観や性格がバラバラでも、人は繋がることができるのだと、アンダーソンの映画は教えてくれるのだ。