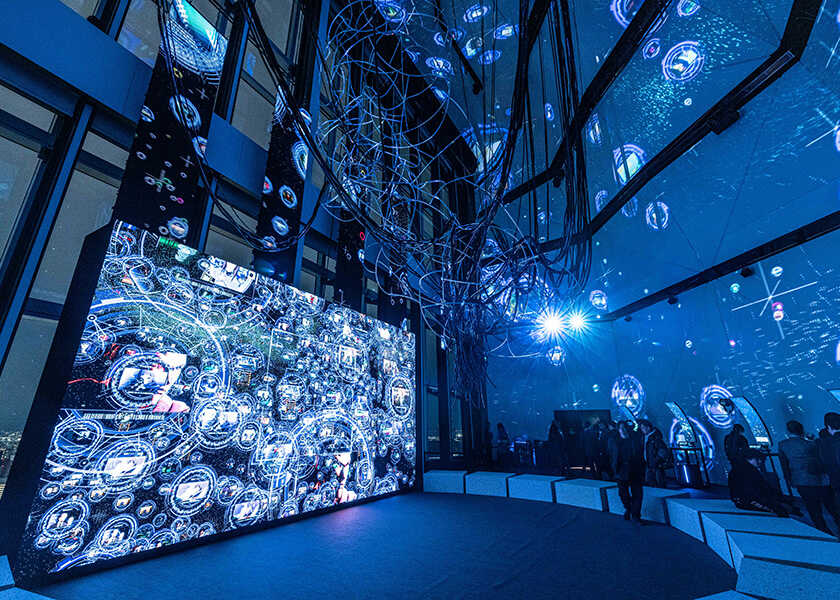犯人と人質に連帯感が生まれる理由とは?『ストックホルム・ケース』
“事実は小説より奇なり”という、ことわざがあるように、日々のニュースを見ていると、加害者も被害者も「なんでこんな行動をするんだ?」という犯罪に出くわす。追い詰められた人間は、常識を超えるレベルの心理状態になるわけで、だからこそ実際の事件は映画にとっても最高の素材になるわけだ。そんな法則を証明してくれるのが、この作品。
- SERIES:
- 今週末は、この映画に胸アツ!
- TAGS:
- 今週末は、この映画に胸アツ! Culture Cinema

『ストックホルム・ケース』
胸熱なポイントは?
“先の読めないスリリングな展開にハラハラする!”
“ストックホルム症候群”という言葉、どこかで耳にしたことがあるのでは? 誘拐や監禁事件で、被害者が長い時間、犯人と一緒に過ごすことで、予想もしない“絆”が生まれてしまう……。そんな現象を表す言葉だ。
なぜストックホルムかというと、この語源になった事件が起きたから。1973年、スウェーデンのストックホルムの銀行に強盗が押し入り、4人の人質が6日間、拘束される事件が発生。やがて犯人と人質が連帯感で結ばれ、ややこしくなった状況から「これはひとつの症候群」と判断された、というわけ。この奇怪な事件をベースに、今作は先の読めないスリリングな攻防を展開していく。
最大のポイントは、犯人役をイーサン・ホークが演じていることかも。ワルを演じても、どこか不器用で憎めない部分がにじみ出るイーサンのキャラによって、人質たちが犯人に共感する流れに妙に説得力をもたせるのだ。
舞台が1970年代のせいか、警察や銀行側の作戦は盗聴など監視方法もアナログでスキがあったりする。交渉もどこかぎこちない。犯人と人質が食料を分けたり、音楽を楽しんだりする“余裕”が生まれるのも、妙にリアルなのである。
心を揺さぶる人間ドラマもさりげなく挿入されるし、要所では衝撃のシーンも! 最後の最後まで事件がどう解決されるのか読めない、犯罪サスペンスの魅力を今作は備えている。
『ストックホルム・ケース』
監督/ロバート・バドロー 出演/イーサン・ホーク、ノオミ・ラパス、マーク・ストロング 配給/トランスフォーマー
2018年/カナダ・スウェーデン/上映時間92分
11月6日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国ロードショー
(C)2018 Bankdrama Film Ltd. & Chimney Group. All rights reserved.